3月になり、20℃ほどの高い気温になる日もあれば、降雪するような寒い日もあります。天気がよく、気温も高くなる日に採集に行くことができたため、そのときの様子を記述します。自宅付近の低標高地(標高約200m)の川沿いの道を歩き、環境がよさそうな場所まで行く途中、暖かいからか道脇のガードレールにテングチョウ Libythea lepita Mooreというチョウ類の一種やクロバエ科のオオクロバエ Calliphora nigribarbis Vollenhovenという種が静止しているのが確認されました。また、近くの茂みには越冬していたと考えられるトンボの一種が見られました。日本では成虫で越冬するトンボ類はオツネントンボ Sympecma paedisca (Brauer)などの3種が知られているようであるため、これら3種のいずれかと考えられます。



今回見られたオオクロバエという種は秋から冬に産卵し、その後早ければ1-2月ごろから初夏にかけて羽化した新成虫が気温が高くなる夏季に高標高地などの気温が低い場所に移動するという生態的特徴が知られています。また、秋から冬に気温が低くなると高地から低地へと大規模な移動をすることが知られており、九州では秋季に大陸から移動していることを思わせる観察事例が報告されています。
本種はこのような移動能力に加え、動物の死骸や排泄物を好んで摂食し、鶏舎や畜舎にも侵入することがあります。過去、高病原性鳥インフルエンザ発生地で冬季に捕獲される主要な双翅目の種が本種であったことや採集された個体の消化管からウイルスが検出された報告もあることから、本種がウイルスを伝搬する可能性は高いと考えられています。このようなことから、本種の季節的な移動や生態の調査は医学・獣医学的にも重要であると考えられます。
参考文献
倉橋弘・末永斂(1997)オオクロバエが秋期に大陸から日本へ飛来し,繁殖することを推測させる長崎での一観察.衛生動物,48:55‒58.
澤邉京子(2020)日本の節足動物媒介感染症対応に関する一連の研究̶高病原性鳥インフルエンザとデング熱の国内流行に注目して̶.衛生動物,71:1-13.

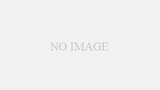
コメント